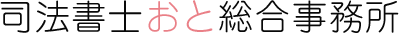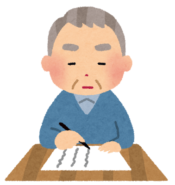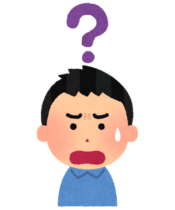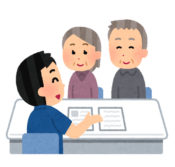成年後見人に選ばれたら最初にする6つのステップ|就任後の流れ!

「後見人の役割」がどのようなものなのかイメージはできていますか?
まだの方は『これを読むだけで成年後見人の仕事や役割が9割わかる!』に目を通してから、本記事を読んでもらえると、より分かりやすくなります。
その役割のイメージが持てれば、何をすればいいのか自分で「考えて」「行動」することができるようになります。
しかし、そうはいっても後見人になりたての頃は、何をしていいのかわからず戸惑ってしまうこともあるでしょう。
そこで、成年後見人に選ばれてからの流れをお話ししたと思います。
目次
1 成年後見人に選ばれてからの流れ(6つのステップ)

では、さっそく流れを見てしまいましょう。
後見の申し立てについての記録を確認する
【重要】本人(被後見人)や関係者から話を聞く
成年後見の登記事項証明書を取得する
管理する財産を預かり、代わりに管理する。
銀行・証券会社・保険会社などへ後見人就任の届出をする
市区町村役場に郵送先の変更手続きをする
この流れを、より深く理解してもうために詳しい流れを説明する前に「後見人の役割」を振り返りたいと思います。
後見人は、被後見人がこれまでと同じように生活が送れるようにサポートすることが役目です。これを実現することが、後見人の具体的な仕事です。
そのためには「なにを知り」「なにを準備」すればいいのでしょうか?
それが自然と頭に浮かぶようになると、おのずと「やるべきこと」が見えてきます。
被後見人をサポートするうえで、はじめにすることは「被後見人(本人)を知る」ことです。これがわからなければ何もできません。
ゴールがどこにあるのかわからなければ、正しい道を進んでいるのか、あとで確認することもできません。ここでいうゴールとは、被後見人がこれまでと同じような生活が送れることです。
そのために、まずは被後見人を知ることからはじまります。
知るための努力は、被後見人(本人)とあなたとの関係によっても変わってくるでしょう。
後見の手続きをする前から、一緒に生活している人と、それまでは数か月に一度くらいしか会っていなかった人では、これからすべきことは変わってきます。
それを念頭に置きながらお読みください。
では、それぞれのステップを詳しく説明していきます。
人によっては工程を飛ばすこともあるでしょう。
2 後見申し立ての記録を確認する(STEP1)
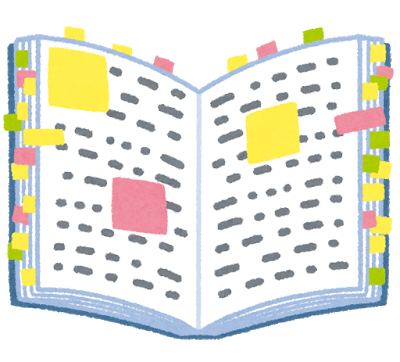
後見人は、家庭裁判所にある後見手続きの記録を見ることができます。
この記録には、被後見人の財産はもちろん、「医師の鑑定書」や「裁判所調査官が、関係者から聞き取った報告書」なども含まれています。
「後見の申し立てに関与していない方」や「申立人ではあったが、専門家や協力者へ手続きをまかせっきりで内容を把握できていない方」は、こちらの記録を読み、これまでの経緯と当面の課題を整理しましょう。
また被後見人が、「どのような財産を持っているのか」「どれくらいの収入や支出があるのか」「実際には誰が管理しているのか」「財産の現状はどうなっているのか」などをご確認ください。
ただし注意してほしいのは、申し立ての時には見つけることができなかった「財産」や「収支」が後になって出てくることはよくあることです。
これですべてだと思わずに「先入観は捨てて」被後見人のサポートにあたるようにしましょう。
【記録を閲覧する際のポイント】
- 被後見人を支援するにあたり「キーパーソンになる人物」は誰なのか?
- 親族や関係者との間で「もめ事」はないか?
この点に注意して目を通すようにしましょう。
3 【重要】本人(被後見人)や関係者から話を聞く(STEP2)

後見人の仕事は、被後見人をサポートすることです。
そして、このサポートは「被後見人(本人)の考え」を尊重したものでなければなりません。
これまでと同じような「自分らしい生活」を送ってもらうためには、被後見人とのコミュニケーションは欠かせません。
かならず、会いに行きましょう。
中には、話してもムダだと会いに行かない方もいるようです。
しかし、それは大きな間違いです。
たとえ判断能力が下がっているとしても、長年繰り返してきたクセや考え方は、随所(ずいしょ)に現れてきます。
一度、会っただけではそれに気づくことは難しいかもしれませんが、「何度も足を運び」「直接会って触れ合う」ことで見えてくるものがあります。
その小さな「シグナル」を読み取りながら、被後見人が望む生活をサポートしていきましょう。
もちろん、その後見人のサポートが必ずしも被後見人が望んでいるものなのかどうかはわかりません。
しかし、だからといって被後見人を知る努力もせずに、投げやりに後見人の仕事をすることだけはやってはいけません。
大切なのでもう一度言います。
被後見人のサポートは、その被後見人の考えを尊重したものでなければなりません。
では次にいきます。次は関係者への聞き取りです。
関係者とはどのような人たちでしょうか?
関係者とは、
- 財産を実際に管理している人
- 本人の身の回りの世話をしている人
- 主治医
- ケアマネージャー
- 施設に入所していれば、そちらの職員
などです。
そして、次のようなことに注意を払い耳を傾けましょう。
- 病歴や通院歴
- 利用している介護サービス
- 支払いが滞っているものはないか
- 普段、どのような生活をしているのか。
- お気に入りの場所はどこか。
- よく観るテレビ番組は何か。
- 被後見人の好きなこと、嫌いなこと。
- どんな性格なのか。
【関係者へ聞き取りをする際のポイント】
被後見人をサポートするうえで、助けになると思う情報を聞きとります。
聞いた内容は忘れないように記録を取るクセを付けましょう。
4 成年後見人であることの証明書の取得(STEP3)

後見人は被後見人に代わって、さまざまな手続きを代行することができます。
しかし、代行するためには、あなたが後見人であることを証明しないといけません。
ただ、どのように証明すればいいのでしょうか?
いくらあなたが、自分は後見人だといっても、誰も信じてくれませんよね。
あなたにとっては、自分が後見人であることは当たり前かもしれませんが、相手にしてみれば目の前にいる人が正式な後見人なのかどうか区別がつきません。
そこで、誰にでもわかるように、後見人であることの証明書を手に入れておく必要があります。
あなたが、後見人に選ばれると、裁判所の嘱託により「後見の登記」がされます。
この後見登記についての登記事項証明書が「後見人であることの証明書」になります。
登記事項証明書は、全国の法務局(本局のみ)で取り付けることができます。
法務局まで出向くことが難しい方は、郵送で取り付けましょう。
その場合は、各都道府県の法務局ではなく、東京法務局後見登記課あてに郵送で取ります。
後見登記について、郵送で対応しているのは東京法務局だけです。
5 管理する財産を預かり、代わりに管理する(STEP4)
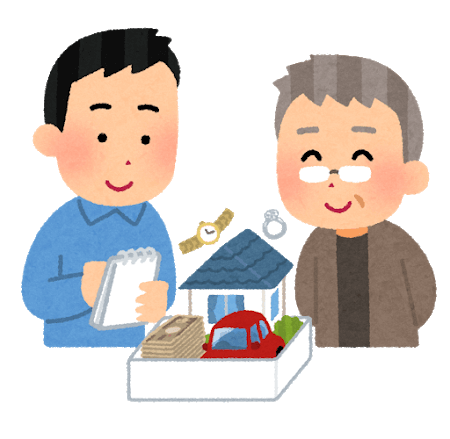
後見人は、被後見人の財産を守る立場にあります。
そのためには、その財産を被後見人から受け取り、代わりに管理・保管する必要があります。
被後見人は、正しい判断ができなくなっています。誰かに騙されて、大切な財産を奪われてしまう危険すらあるわけです。
そうならないためにも、「財産の占有を確保し」大切に管理しなくてはいけません。
具体的には、次のものを被後見人から預かり、金庫や貸金庫で大切に保管しましょう。
- 預金通帳
- キャッシュカード
- 銀行の届出印
- 権利証・登記識別情報
- 実印
- 印鑑登録カード
- マイナンバーカード
- 保険証書
- 年金手帳
など。
※保佐人や補助人は管理権限が与えられている財産のみ保管することになります。
これらの財産を本人(被後見人)以外が管理している場合、その人に財産の引き渡しを求め、協力をあおぎましょう。
その要求を、すんなり受け入れてくれればよいのですが、そのようにうまくいくケースばかりではありません。
これまで自由にできていた被後見人の財産を「手放したくないと考える人」もいます。
その時は、後見人がどのような立場にあるのか、被後見人のために財産の管理をしなければならないことを丁寧に説明し、協力を取り付けましょう。
それでも引き渡しを拒絶された場合は、調停や訴訟を検討することになります。
6 銀行・証券会社・保険会社などへ後見人就任の届出(STEP5)

後見人は被後見人の財産を管理する権限があります。
被後見人に代わって「銀行預金を引き出したり」「光熱費の引き落とし口座を変えたり」することができるわけです。
しかし、これらの銀行取引ができるのは、原則、「名義人本人」だけです。
名義人以外の者が、これらの行動をとっても、銀行は認めてくれません。
当然といえば、当然です。
しかし、それでは後見人としてのサポートをすることができません。
毎回、窓口で後見人であることを説明すれば、これらの行為は認められますが、それでは手間がかかって仕方がありません。
そこで、銀行取引をスムーズに行えるように、銀行に対し事前に後見人に選ばれたことを届けておくといいでしょう。
保険会社や証券会社も同じです。
銀行や保険会社に所定の届出書がありますので、それを使ってください。
また、通帳やキャッシュカードを後見人が管理していたとしても、「ほかの親族」が被後見人と一緒に銀行の窓口へ行き、「お金を引き出してしまったり」「保険契約を解約し、解約返戻金を受け取ったり」してしまう可能性もあります。
それを防止するためにも、成年後見人に就任したら、すぐに銀行や保険会社、証券会社などに届出をするようにしましょう。
7 市区町村役場へ送付先変更の手続き(STEP6)

後見人は、被後見人が年金やその他の収入を受け取れるように、そして、病気やケガなどの際には、病院で受診できるように配慮する義務があります。
そのため、国民年金現況届、障害者医療証、健康保険証などを、被後見人に代わって後見人が受け取れる体制を整えましょう。
「年金現況届出を出さずに年金がもらえなった」
これでは笑えません。
関係各所へ、後見人に選ばれたことの報告とともに、郵送先の変更の手続きも忘れずに行いましょう。
ただし役所によっては、このような取り扱いをしてくれないこともあるので、個別にどうするか検討し、対策を練ることが求められるでしょう。
8 まとめ
いかがでしたでしょうか。
後見人に就任してからの流れを、駆け足で説明させてもらいました。
こちらを読みながら、ゆっくりでいいので確実に進めていきましょう。
そして忘れないでいただいきたいことは、これらの作業はすべて被後見人(本人)がこれまでと同じように生活をおくれる環境を整え、被後見人の利益を守るためにあるのだということです。
もし壁にぶつかったら、成年後見制度の目的を思い出しましょう。