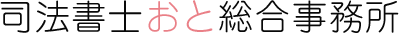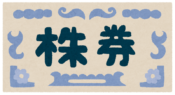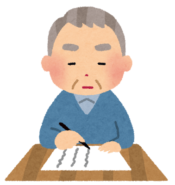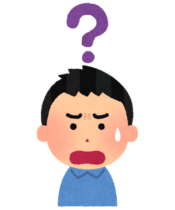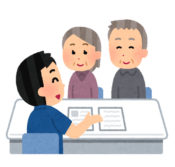相続不動産に古い抵当権がついていて売れない!を解決する方法

『相続した不動産に古い抵当権がついていて、売れない』
しかも、
- 日付は明治とある
- 銀行ではなく、個人の名前が書いてある
- ほかにも賃借権の仮登記というものがついている
「これは、どうすればいいの??」
相続の仕事にかかわっていると、このような事例も珍しくありません。このような場合、原則どおりのやり方では、抵当権を消せないケースがほとんどです。
そこでこのページでは、長年、放置された抵当権を消す「裏技」をご紹介します。
目次
1 休眠担保権とは?

休眠担保権とは、支払い日から20年以上、放置されてしまった担保権(抵当権や質権など)のことです。
なぜ、このような事が起こるのでしょうか。
それは、その時の感情に起因しています。誰でも「お金を貸したとき」は必至になって担保を取るものです。返してもらえなければ損をしますから、当然の行動です。
一方で、お金を回収して(返済して)「担保を消すとき」は、「みんな」のんびり構えています。債権者(お金を貸した人)は、それもうなずけます。お金を返してもらっているので、担保権が消されようが残っていようが「どうでもいい」わけです。
早く消したいはずの所有者はどうかというと、やはり呑気に構えています。
- 時間ができたら抵当権を消そう
- 借金は返済したわけだから、急ぐ必要はない
- 「罰則もないし」「誰からも怒られないし」放置してもいいだろう
と考えてしまいます。そして、長年に渡って、放置された担保権が生まれてしまうのです。
2 抵当権の抹消は「所有者」と「抵当権」の協力が必要
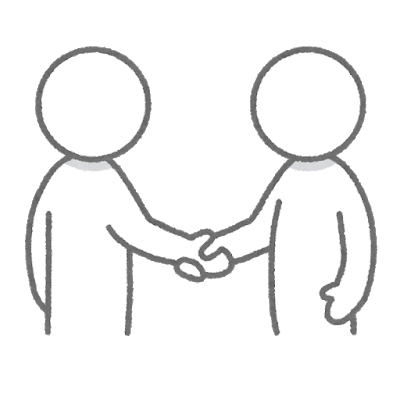
相続した不動産に抵当権がついていたら、誰でも心配になるものです。
- 借金があったのだろうか
- もし、滞納になっていたら不動産を取られてしまうのだろうか
- このままでは、不動産を売ることもできない
そして、次のような感情が浮かびます。
「なんとか抵当権を消したい」
でも残念ながら、「長期間」放置された抵当権は簡単には消せません。
その最大の理由が、抵当権の抹消登記は「(不動産の)所有者」と「抵当権者(お金を貸した人)」のふたりで協力して申請しなければいけないからです。
例えば、あなたが相続した不動産に抵当権がついていたとします。
その抵当権は、あなたの曾祖父(ひいおじいちゃん)がつけたものでした。抵当権者の名前を見ても、誰だかわかりません。どうやって、連絡を取ればいいのでしょう。それよりも、その人は生きているのでしょうか。
このようなケースのやっかいなところは、「相続人が抵当権者を知らず」、さらにはやっとのことで調べ上げても「その人が死んでいる」ケースが多いことです。
そうすると、原則どおり「所有者」と「抵当権者」の共同申請で抹消することはできません。
3 相続不動産に付いている古い抵当権を消す4つの方法
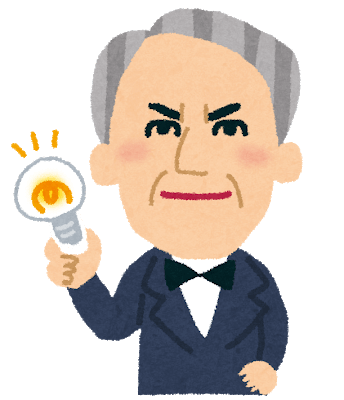
『抵当権者が見つからず「抵当権」が消せない』
頭を抱えてしまいますね。でも大丈夫です。法はこのようなケースでも抵当権を消す方法を用意しています。
- 訴訟
- 除権決定
- 債権証書・受取証書がある
- 供託
ここでのポイントは、「抵当権者が行方不明で連絡も取れず登記について協力を得られない状況」というところです。
抵当権者の居場所がわかっていれば、この方法(訴訟を除く)は使えません。
この4つの方法について詳しく見ていきます。
3.1 訴訟【相続不動産の抵当権を消す方法1】
これは文字通り、相手を訴えて、裁判所から抵当権がないことを認めてもらい抵当権の登記を消していきます。
訴訟において一番の難関は、自分の言い分を客観的に証明しなければいけないところです。訴訟では「あなたの主張と証拠」がすべてです。勝敗のポイントは「立証責任」にあるといってもいいでしょう。
わかりにくい点なので、詳しく説明します。
「証明できなければ勝てない」
一度は聞いてことがあるでしょう。でも、これを聞いて不思議に思うことはありませんか。「ある事実」について、お互いが証明できなければ、どちらが不利益を受けるのでしょうか。
例えば、「ある時計」について「ふたりの男性」が「それは自分のものだ」と主張しているとしましょう。ふたりとも「自分のものであること」が証明できませんでした。
さて、どちらが不利益をうけるのでしょうか。それは「証明する責任」を負っているほうです。
話しを戻して考えてみましょう。抵当権の抹消に関する訴訟では、(その抵当権が消滅していることを)どちらが証明する責任を負っているのでしょうか。
これは、「訴訟物という裁判のテーマ」によって変わってきます。
訴え方によって、あなたが抵当権の消滅を証明しないといけない場合と、そこまでは証明しなくてもいい場合に分かれます。
裁判のテーマ次第で、あなたの運命が大きく変わってしまうのです。証明する範囲が増えれば増えるほど、大変です。
訴訟を選択するケースでは、行動を起こす前に必ず立証責任の範囲を検討しましょう。ここを詳しく説明すると、本が一冊書けてしまうので、このあたりで終わります。
3.2 除権決定【相続不動産の抵当権を消す方法2】
除権決定とは、裁判所にその権利が消滅していること認めてもらうことです。
この決定をもらうためには、裁判所へ「公示催告の申し立て」という手続きをします。いろいろな単語がでてきて混乱しますね。
公示催告とは、かんたんに言ってしまうと「抵当権者は、2か月以内に名乗り出てね」と裁判所が公告をすることです。その期間内に抵当権者が名乗り出ないと、裁判所は(抵当権は消滅しているとの)除権決定をします。
先ほども言いましたが、この手続きは抵当権者が行方不明のケースを想定しています。
しかも、効果は絶大です。それは、つまり決定がでるまでのハードルの高さを表しています。
どういうことかというと、この決定を裁判所に出してもらうためには、抵当権が消滅していることを「あなた」が証明しないといけません。抵当権が消滅しいるとわかるだけの資料を集め、裁判所に提出します。裁判所が消滅しているとの心証を得られるだけの資料がそろわなければ、この決定はでません。
不動産を相続し、その不動産に古い抵当権が付いている場合、ふつう相続人はその抵当権について情報を持っていません。
その身に覚えのない抵当権について、消滅しいることのわかる資料を提出できるケースは稀でしょう。そのため、この手続きは実務上、利用させることは多くありません。
3.3 債権証書と受取証書がある【相続不動産の抵当権を消す方法3】
条件さえ満たしていれば、4つの中で一番簡単です。その条件とは「完済しいることがわかる書類がある」ことです。
抵当権とは、貸したお金が返ってこなかった場合に備えて設定します。要は「担保」です。ということは、お金が返ってきたら用なしです。
そこで、「完済している証明書があれば、土地の所有者だけでの申請を認めてもいいだろう」という特例があるのです。
ただし、この完済証明書を相続人が持っていることは、やっぱり稀です。そのため、除権決定と同じように、この方法が使われることも多くありません。
3.4 供託【相続不動産の抵当権を消す方法4】
供託とは、国の機関である供託所に、お金を預けることです。その預けたことをもって、債務を免れる仕組みを弁済供託といいます。
お金を借りれば、借主は「お金を借りた人(貸主)」にお金を返します。しかし、その貸主が行方不明になってしまうと返済することができません。
支払いができないと、借金が残ったままです。支払日が経過すれば、延滞金もついてしまいます。それでは困ってしまいますね。
そこで、その不都合を回避する方法として、(弁済)供託の制度が作られました。
上記3つの方法は、「すでに弁済が終わっていること」を前提とした手段ですが、この供託は「借金が残っていること」を前提としています。
残っている借金の全額を供託して抵当権を消します。利息も損害金もすべてです。
そして、この方法で抵当権を消すためには抵当権者が行方不明という条件の他に、もうひとつ条件があります。それは、借金の「支払日から20年が経過している」ことです。
この要件を満たしていなければ、所有者が「単独」で抵当権を抹消することはできません。
4 まとめ
長い間ずっと放置された抵当権を抹消するのは、時間と手間がかかります。
しかし、逆に考えると時間と手間をかければ消すことができます。
諦めずにどのような方法があるのか、どの方法が自分に最適なのかを考え、手続きを進めていきましょう。